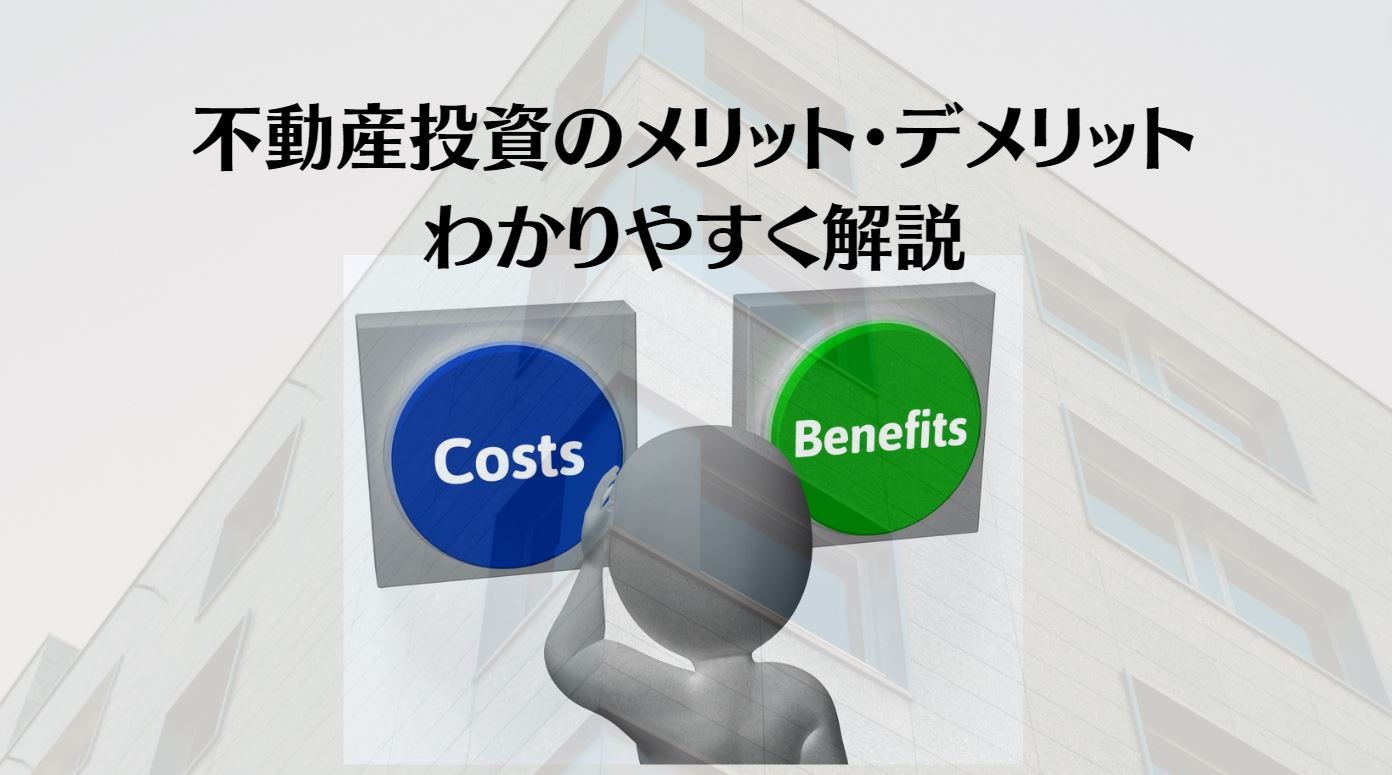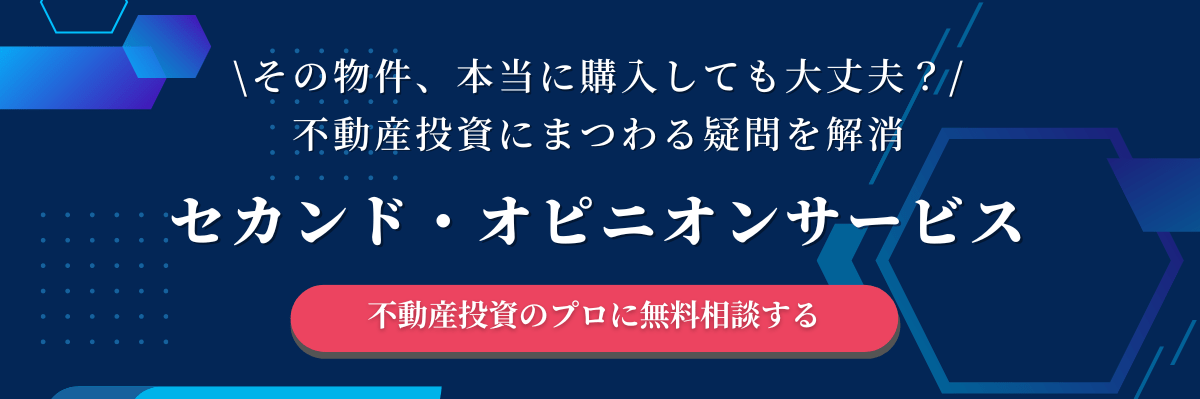不動産投資を行うメリットには、どのようなものがあるかご存知でしょうか。
金融機関に預貯金をしてもほとんど利子がつかず、年金に対する不安なども高まり、不動産投資は長期間の資産形成商品として注目されています。
また、不動産投資は、株式やFXなどハイリスク・ハイリターンの金融商品に比べてミドルリスク・ミドルリターンの資産運用先の一つとしても人気を集めています。
今回は、不動産投資の8つのメリットや、デメリット・リスクについて解説します(監修:税理士・鈴木まゆ子)。
以下の記事も併せて参考になさってください。
不動産投資のバイブル
- 不動産投資に興味があるけど何から始めていいか分からない…
- 営業マンのいうことを鵜呑みにして失敗したくない…
- しっかりと基礎から学び、できる限りリスクを避けたい…
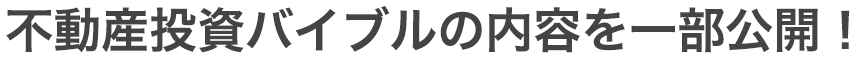
- 今は不動産投資の始めどきなのか?
- 安定収益を得るための不動産投資物件の選び方
- 不動産投資の失敗例から学ぼう
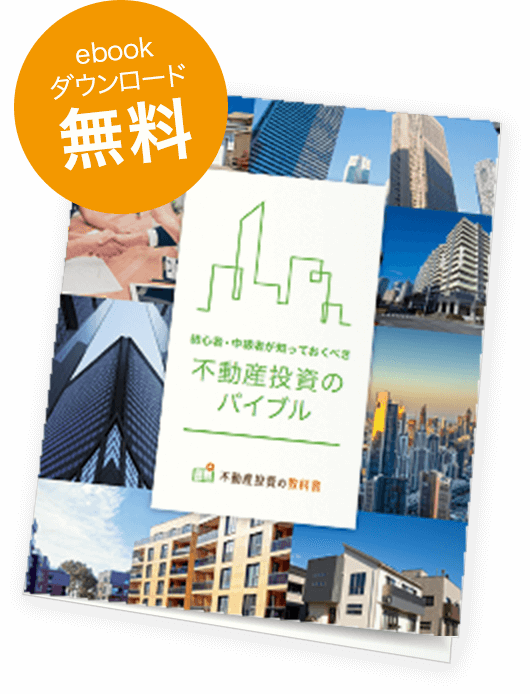
1、不動産投資の8つのメリット
不動産投資にはインカムゲインとキャピタルゲインという投資方式があります。
インカムゲインは、不動産物件を購入・所有し、賃貸として貸し出して家賃収入を得る投資方式です。現在の日本では、このインカムゲインが主流になっています。
一方、キャピタルゲインは、不動産の売買によって売却益を得る投資方式です。具体的には、不動産を購入した価格よりも高い金額で売却することで利益を得る投資方式となります。
本章では、不動産投資の主流となるインカムゲインを中心に、以下の不動産投資の8つのメリットを紹介します。
- 私的年金の確保ができる
- インフレに強い
- 安定した不労所得を得られる
- 高利回りが期待できる
- 相続・贈与税対策として有効である
- 生命保険の代わりになる
- 借入により少額自己資金から始められる
- 所得税の節税効果がある
(1)私的年金の確保ができる
新型コロナウイルスに端を発した不況の影響もあり、将来の不安はより一層増しています。
そもそも日本の公的年金は、財源不足と少子高齢化の影響で、今後は支払う保険料が増加しながら受給額が減っていく可能性が高いとされています。また、受給年齢も引き上げられてきており、年金に対する不安が高まっています。
もし、今のうちから不動産投資を始めれば、賃料収入で長期的・安定的に資産形成し、私的年金という側面から老後に備えることができるのです。退職後もゆとりあるセカンドライフを楽しむことができるでしょう。
(2)インフレに強い
日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付などもあり、インフレの懸念は高まっています。
そもそも、政府や日銀は「2%のインフレ目標」を掲げています。インフレになると貨幣価値が下落するため、預貯金は不利となり、不動産のような実物資産が有利となります。
一般的に、地価が上昇すると物価も上昇する傾向にあります。令和5年地価公示の結果は以下の通りです(住宅地)。
- 東京圏:上昇率 2.1%
- 大阪圏:上昇率 0.7%
- 地方圏:上昇率 2.3%
- 名古屋圏:上昇率 1.2%
- 札幌市・仙台市・広島市・福岡市:上昇率 8.6%
以上の傾向は、土地に対して貨幣価値が下落していると捉えることができます。資産を守るためには不動産投資が有効と言えるのです。
(3)安定した不労所得を得られる
不動産投資の最大の魅力は、長期間にわたり安定した家賃収入を得られることです。
一気に大きな利益を得ることは難しいですが、月々安定した収入を得られるためローンで購入した場合でも返済しながら資産を築くことができます。
金利や株価、地価などは大きく変化している中、マンションやアパートの賃料水準が大きく変動することはほとんどありません。
(4)高利回りが期待できる
日本は長らく低金利が続いており、預金より少しでも高い利率の金融商品や投資対象を求める方が多くいらっしゃるでしょう。
しかし、株式投資やFX、外貨預金などの投資商品では、ハイリターンが得られる反面、ハイリスクでもあります。
不動産投資なら、家賃収入により安定して利回りが得られるため、他の投資方法と比較しても魅力的といえるでしょう。
首都圏では、ワンルームマンションで5~7%ほど、一棟アパートでも6~9%ほどの利回り(表面利回り)が期待できます(参照:収益物件 市場動向 年間レポート 2022年)。
(5)相続・贈与税対策として有効である
相続や贈与の税金は、非常に大きな負担です。特に現金や有価証券の場合は、時価に対して課税されるため税額も高くなります。
しかし、不動産の相続や贈与の場合、固定資産台帳や路線価などから算出した評価額に対して課税されます。
不動産の相続税法上の評価額は、実勢価額(時価)に比べて低くなる傾向にあるのが一般的です。現預金や有価証券を相続・贈与した場合よりも、納める税金の額を少なくすることができます。
建物の場合は、およそ50〜60%で評価され、土地は公示地価の80%位で評価されます。
また、投資用不動産で第三者に賃貸することで、評価額がさらに借家権割合の30%が控除されます。
この他、賃貸用物件がある宅地であれば、小規模宅地等の特例の適用により、土地面積200㎡を上限に評価額を50%下げることができます。不動産投資は相続・贈与税対策として有効といえるでしょう。
それでは、一例として相続税評価額の計算式を見ていきましょう。
| 相続税評価額の計算式 | |
| 建物の評価額 | 建物 × 固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合) |
| 土地の評価額 | 土地×路線価評価額(公示価格の80%)×(1 – 借家権割合)× 小規模宅地等の特例の適用による減額割合) |
| 相続税評価額 = 建物評価額 + 土地の評価額 | |
購入価格2,000万円の投資マンションの場合(建物実勢価額:1,200万円/土地800万円)
| 建物:1,200万円 × 0.5 ×(1−0.3) | 420万円 |
| 土地:800万円 × 0.8 ×(1 – 0.3)× 0.5 | 224万円 |
| 相続税評価額 | 420万円 + 224万円 = 644万円 |
不動産の相続税について詳しく解説した記事を併せてご参照ください。
(6)生命保険の代わりになる
不動産の購入資金について、金融機関から融資を受ける場合は、団体信用生命保険に加入しなければなりません。
万が一、ローンの返済期間中に死亡または高度障碍者となった場合、団体信用生命保険が適用されローンの残債は保険金から返済されます。
残されたご家族には、無借金のマンションを残し、毎月安定した家賃収入もあります。
残される家族には保険のような役割も果たせるのは、数ある投資対象の中で、不動産投資の大きな特徴と言えるでしょう。
(7)借入により少額自己資金から始められる
不動産投資は、商品である不動産自体を担保にし、金融機関から購入資金を借入することが可能です。ローンを活用すれば、少額の自己資金で不動産を購入することができ、家賃収入の収益を得ることができます。
借入により少額の自己資金で収益を得ることができる点は不動産投資のメリットの一つといえるでしょう。
株式投資やFX投資などは、保証金を準備すれば信用取引などの例外もありますが、基本的に借り入れて投資することはできません。そのため、手元にそれなりのまとまった投資資金が無ければ利益を得ることは難しいでしょう。
しかし、不動産投資は少ない資金であっても、融資を受けて始められ利益を得ることができます。これは、不動産投資ならではの特徴です。
不動産投資ローンについて詳しく解説した記事を併せてご参照ください。
(8)所得税の節税効果がある
不動産投資では、給与所得とは別に、家賃収入を「不動産所得」として申告することが可能です。
不動産経営での年間収支が計算上で赤字になった場合は、給与所得など他の所得と損益通算をして赤字の不動産所得と黒字の他の所得を相殺することができます。結果、所得全体の金額が下がるため、納付すべき税額を低めに抑えることができるのです。
節税できるのは所得税だけではありません。住民税は、所得税の計算の基礎となった所得額から算定されます。つまり、所得税を節税すれば、住民税も節税することになります。
不動産所得の計算においては、以下の費用を必要経費として計上できます。
・租税公課
・損害保険料
・減価償却費
・修繕費
・借入金利息
・管理費
・広告宣伝費
・交通費
・通信費
・新聞図書費
・接待交際費
・消耗品費
・税理士に依頼した場合にかかる費用
2、不動産投資のリスク・デメリット
前章にて、不動産投資のメリットを細かく紹介いたしました。
一方、メリットがある裏側にはデメリットが存在します。不動産投資の場合、デメリットというより「リスク」という言い方をした方が正しいかもしれません。
本章では、おもな不動産投資のデメリット(リスク)を4つ紹介いたします。
(1)空室リスク
不動産投資の8つのメリットにて、安定した不労所得を得られると紹介しました。
しかし安定した不労所得が得られるのは、当然その不動産に入居者がいる場合です。入居者がいなければ安定した不労所得どころか安定して赤字となってしまいます。
本来毎月の収入を増やすために不動産投資を始めたとしても、赤字となってしまっては本末転倒です。
空室リスクを回避するために、空室が出にくい物件を選ぶことが大切です。
なお、空室になりにくい不動産投資物件の選び方についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
(2)流動性リスク
投資における流動性とは、投資対象の換金の容易さを表す要素のことです。つまり、不動産が売却しやすいのかそうではないのかということで、一般的に不動産は売却しにくい投資対象と言われています。
不動産には株式のような市場がなく、多くの場合が不動産会社を通して買手を募ることになり、時間がかかるためです。
目安として、3~6ヶ月ほどかかるでしょう。また、希望の売却価格で不動産が売却できるというわけでもありません。
これは、不動産投資をする際のリスクというより不動産を売却するときのリスクですが、不動産投資を成功させるためには、出口戦略まで考えることが必要です。
もちろん入居者がいればインカムゲインである毎月の収入を得ることができます。
しかし、資産の売買差益であるキャピタルゲインも得たいと考えるのであれば、売却まで考慮した上で不動産を購入するべきでしょう。
(3)災害リスク
災害リスクには人災的なものと天災的なものがあります。
人災的なものとしては
- 火事
天災的なものとしては
- 地震
- 津波
- 台風
などがあります。これらのリスクは、残念ながらオーナー次第で全てなんとかなるというものではありません。
火事に至っては入居者の不注意・もしくは近隣からの類焼などが考えられますし、天災に至っては自然現象なのでどうしようもありません。
そのため、大切なことはこれらの災害に強い不動産を購入する・保険に加入するなどの、予め災害を予測した不動産経営を行うということです。
災害リスクは基本的には確率が低いため、そこまで過度に神経質になる必要もありませんが、もし災害によって不動産に被害が出れば大損する可能性があります。
積極的にリスクヘッジを検討しましょう。
(4)家賃下落リスク
新築の物件なら家賃が高く、ある程度築年数の経った物件なら家賃は安くなります。このように不動産投資は、購入したて(新築当初)の家賃設定がその先もずっと続くというわけではありません。
家賃が下落する原因として、
- 建物の経年劣化
- 需要の低下
- 立地、利便性がよくない
などがありますが、これらも予めの予測を立てながら不動産投資を始めることが大切です。そのためには良質な不動産投資会社、信頼できるパートナーを見つけることがなにより重要となるでしょう。
本章では不動産投資の4つのデメリット(リスク)を簡単に紹介しましたが、その対策まで知りたいという方は不動産投資のリスクについて詳しく解説した記事を合わせてご覧ください。
3、物件別不動産投資のメリット・デメリット
不動産投資にはアパートやマンション、新築や中古など、いろいろな物件があります。
それぞれのメリット・デメリットを簡単に紹介します。
- 新築区分マンション
- 中古区分マンション
- 新築一棟アパート
- 中古一棟アパート
(1)新築区分マンションのメリット・デメリット
①メリット
新築区分マンションのメリットは、都心であれば需要が高いため入居率が高いということです。東京都の人口は2030年を超えても増え続けると言われており、都心の入居需要が廃れる心配はあまりないでしょう。
また、新築であるために家賃相場を高めに設定できるということもメリットです。
②デメリット
新築のマンションは高額です。融資の額にもよりますが、初期費用や購入金額が高くなるため、利回りが低くなってしまう可能性があります。
(2)中古区分マンションのメリット・デメリット
①メリット
中古区分マンションは、新築区分マンションよりも割安で購入できるため利回りが高いです。
中古でも都心の需要はあるため、空室が出にくいというのもやはり強みでしょう。
②デメリット
目立つデメリットはあまりありませんが、強いていうなら突発的な修繕費がかかる場合があるということです。
築何年のマンションなのか、次の大規模修理はいつなのかを把握した上で購入することを心がけましょう。
(3)新築一棟アパートのメリット・デメリット
①メリット
新築一棟アパートのメリットは、空室になりにくく、利回りは区分マンションよりも高めになるということです。
②デメリット
デメリットは、構造にもよりますがアパート建築にかかる費用と空室次第ではキャッシュフローが赤字に転じたときのリスクが大きいということが挙げられます。
(4)中古一棟アパートのメリット・デメリット
①メリット
中古一棟アパートも新築一棟アパート同様のメリットがありますが、新築よりも利回りが高いです。
月々の収入(キャッシュフロー)を最も多く得たいのであれば、入居率次第では中古一棟アパートが一番でしょう。
②デメリット
これも中古区分マンション同様、突発的な修繕費が発生する可能性があります。
4、不動産投資による所得税のシミュレーション
それでは、不動産投資による不動産所得と給与所得が損益通算した場合の所得税のシミュレーションを見ていきましょう。
不動産情報や借入条件を前提にて算出しました。
不動産情報 | |
物件価格 | 15,000,000 |
家賃(月額) | 80,000 |
管理費・修繕積立金(月額) | 16,110 |
賃貸管理会社管理費(月額) | 4,320 |
借入条件 | |
自己資金 | 5,000,000 |
借入金額 | 10,000,000 |
借入金利(変動) | 3.00% |
物件築年(西暦) | 2004 |
建物構造 | 47 |
ローン年数 | 20 |
経過年数 | 10 |
残存耐用年数 | 37 |
税務上耐用年数 | 39 |
年間収入額 | ||
家賃収入額 | ① | 960,000 |
給与所得 | ② | 5,100,000 |
収入合計額(① + ②) | ③ | 6,060,000 |
不動産諸経費 | ||
固定資産税 | ④ | 60,000 |
管理・修繕費 | ⑤ | 193,320 |
PM会社費用 | ⑥ | 51,840 |
損害保険料 | ⑦ | 20,000 |
減価償却費 | ⑧ | 420,000 |
借入金利子(建物取得対応部分のみ) | ⑨ | 283,660 |
税理士報酬 | ⑩ | 50,000 |
合計(④~⑩合計) | ⑪ | 1,078,820 |
所得税計算 | ||
不動産所得(① – ⑪) | ⑫ | ▲118,820 |
給与所得(⓶) | ⑬ | 5,100,000 |
所得額合計 | ⑭ | 4,981,180 |
社会保険料控除 | ⑮ | 1,500,000 |
基礎控除 | ⑯ | 380,000 |
控除額合計(⑮ + ⑯) | ⑰ | 1,880,000 |
課税対象となる所得額(⑭ – ⑰) | ⑱ | 3,101,000(千円未満切捨) |
所得税額 | ⑲ | 212,600 |
復興特別所得税額(⑮*2.1%) | ⑳ | 4,464 |
源泉徴収額(年末調整後) | ㉑ | 209,200 |
納付すべき所得税額(⑲ + ⑳ – ㉑) | ㉒ | 7,800(百円未満切捨) |
通常、不動産所得を得ると、収入が増えるため、納める税金も増えることになります。しかし、上記ケースでは、必要経費を漏れなく計上した結果、所得税の増額を極力抑えることに成功しています。
特に不動産購入時には費用がかかるため、購入した年の所得税は節税効果が高いと感じるでしょう。
会社員の方が不動産投資した場合の確定申告について詳しく解説した記事を併せてご参照ください。
まとめ
今回は不動産投資のメリットについて紹介しました。
不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンと言われる資産運用として人気ですが、具体的にどのようなメリットがあるのかを理解していない方も多いです。
同時に、デメリットやリスクについても理解しなければなりません。メリットだけに目が行きがちな人は、気づいた時には不動産投資で大きな失敗をしています。
不動産投資のメリット・デメリットをしっかりと理解して、賢い不動産投資をしていきましょう。