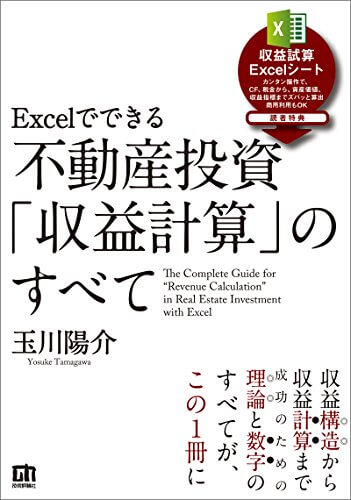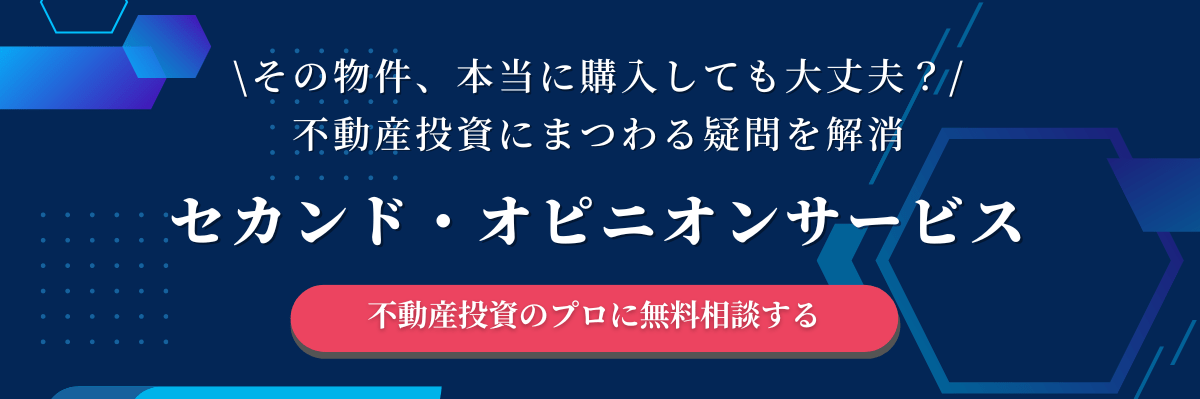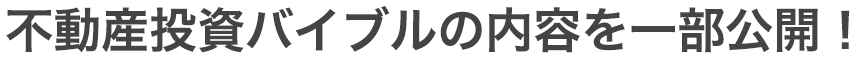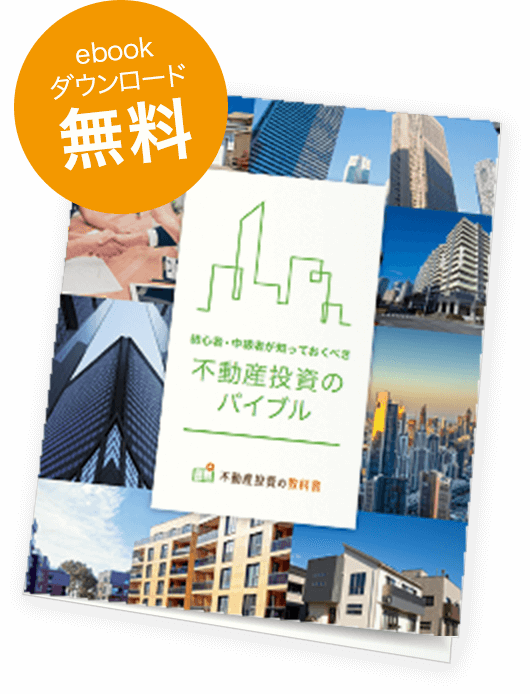不動産投資で節税効果は得られるのでしょうか?
不動産投資を進めるときには、キャッシュフローを増やして利益を上げることが重要ですが、「節税効果」も無視することはできません。
不動産投資を上手に利用すると、いくつかの税金での節税を期待できます。
反対に、不動産投資によって、税金が増えてしまうこともあります。
では、どのような場合に節税することができて、どのような場合に税金が増えてしまうのでしょうか。
本記事では、
- そもそも節税はできるのか
- 不動産投資で節税できる3種類の税金とその仕組み
- 不動産投資でどこまで節税ができるのか
- 不動産投資で節税する際の注意点
などについて、不動産についてのコンテンツを発信している当メディア「不動産投資の教科書」が詳しく解説します。
本記事が、不動産投資の節税に悩んでいる方の手助けになれば幸いです。
不動産投資の教科書代表YouTube「山本社長の不動産事件簿」では、不動産投資の実際にあった悪質な営業担当に騙された話や、良くない物件を買ってしまった失敗談をお話ししています!
目次
1、不動産投資はそもそも節税対策になるのか

「不動産投資をすると、節税になるの?」と気になっている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産投資は、他の投資と比べて高額な費用が必要になるため、できる限りの節税はしたいものです。
結論としては、不動産投資を行うことで、節税することが可能です。
不動産所得は、給与所得と合算することができるので、不動産所得が赤字の場合は、給与所得から不動産所得を差し引くことができます。その結果として、所得金額が小さくなり、所得税を減額することができるといった仕組みになります。
不動産投資によって、必要経費を考慮した上で不動産所得が赤字であれば、節税できるということです。
反対に、不動産投資による所得が黒字の場合は、所得から差し引きすることはできません。
総所得が上がるとともに、税金が増えてしまうことになります。
簡単に節税の仕組みを解説しましたが、さらに具体的な内容について、次章で詳しく解説します。
2、不動産投資による具体的な節税対策

まずは、不動産投資をすると、どのような税金の節税が期待できるのか確認しましょう。
本章では、どの税金が節税対策になるのか、どのような仕組みで節税されるのかを紹介します。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
不動産投資によって節税効果があるのは、上記の3つの税金です。
各税金について、詳しく見ていきましょう。
(1)所得税
所得税は、給与や事業、投資などで、何らかの「利益」が出たときにかかる税金です。
所得税を計算するときには、給与所得以外の投資による所得など、何らかの利益が出た場合は合算して計算します。
給与所得以外の所得のうち、どれかがマイナスになっていたら、他の所得を減らすことができるのです。
つまり、不動産投資による所得が赤字になっていたら、給与収入から不動産所得の赤字分をマイナスにすることができます。
下図のように、アパート経営の所得が、固定資産税や修繕費用の経費によって「マイナス」になっていたら、その分給与所得が減ることになります。
結果として、全体として給与所得にかかる所得税が減るのです。
不動産所得のうち、以下のようなものは必要経費とみなされ、不動産投資で得た収入から差し引くことができます。
- 登記費用
- 仲介手数料
- 税金(不動産取得税・固定資産税・都市計画税など)
- 損害保険料(火災保険や地震保険など)
- 修繕費(入居者が退去時のクリーニング費用など)
- 賃貸管理会社管理費
- 建物の減価償却費
- マンション管理会社管理費(管理費や修繕積立金など)
- 税理士や司法書士などへの報酬
- その他経費(交通費・ガソリン費用・交際費など)
- 賃貸開始後に支払った借入金の利息(融資を受けた場合)
所得税は、不動産所得から必要経費を差し引いた上で、計算しましょう。
ただし、不動産購入2年目以降は、計上できる経費が少なくなります。
例えば、以下の費用は購入時のみ発生する経費であり、2年目以降は経費として扱えません。
- 登記費用
- 不動産取得税
- 仲介手数料
必要経費に換算できる項目が少なくなり、不動産所得がプラスになった場合は、上がった分の税金が増えてしまうので注意が必要です。
(2)住民税
住民税は、所得に応じて都道府県や市町村に支払う地方税です。
「所得の10%程度」が、住民税として課されます。
所得税が低くなれば、住民税も下がることになります。
この仕組みが分かれば、不動産投資によって住民税を節税することは容易です。
不動産投資の住民税について、詳しくは「不動産投資で住民税が安くなる仕組みと4つの注意点」こちらの記事で紹介しておりますので、あわせてご参照ください。
(3)相続税
相続税は、一定以上の財産を相続した場合にかかる税金です。
相続税を計算するときは、相続税評価額というものを用います。
不動産投資をすると、相続税の節税が容易です。
不動産の相続税評価額は、現金や預貯金よりも低いので(土地なら8割、建物なら7割程度)不動産を購入するだけで、その圧縮分が節税につながります。
現金で相続するよりも、不動産で相続した方が、相続税を抑えることができるのです。
また、不動産を賃貸に出すと、借地権や借家権の割合を、評価額から減らすことができます。
小規模宅地の特例を受ければ、より大きな評価額の減額が可能です。
不動産を購入して賃貸に出すだけで、大きく相続税を減らすことができるということになります。
不動産投資による相続税対策について、詳しくは「不動産投資「早すぎる相続税対策」はなぜNGなのか」こちらの記事で紹介しておりますので、あわせてご参照ください。
3、不動産投資で節税するためのポイント4つ

不動産投資には、さらに節税対策が期待できるポイントが4つあります。
4つのポイントは、以下ようなことが挙げられます。
- 減価償却費と節税
- キャッシュフローのシミュレーションが重要
- 法人化することでさらに節税効果を期待できる
- 「青色申告」でさらに節税対策できる
(1)減価償却費と節税
不動産投資によって給与所得や事業所得などの他の所得から差し引きができるのは、「不動産所得が赤字」の場合です。
ただし、不動産投資の場合、「赤字=キャッシュフローがマイナス」という意味ではありません。
不動産には「減価償却費」という、実際には支払わない経費が認められるからです。
減価償却費を上手に利用すると、キャッシュフローをプラスにしながらも、税務上の不動産所得をマイナス(赤字)にすることもできます。
そうすれば、他の所得から差し引くことができて、所得税や住民税を減らすことができます。
不動産投資によって節税するためには、不動産投資を「賢く赤字にすること」が重要です。不動産投資が赤字かどうかは、手元の現金が増えたか減ったかではなく、税務上の収支(帳簿上)によって判断されるということを、押さえておきましょう。
(2)キャッシュフローのシミュレーションが重要
不動産投資で賢く節税するためには、どのようなスキルが必要なのでしょうか?
要求されるのは、「不動産投資におけるキャッシュフローのシミュレーション」です。
不動産を購入するとき、以下のようなお金について、正確に計算する必要があります。
- 年間の収入がどのくらいか
- どのような経費がどれだけかかるか
- どのくらいの税金が発生するか
- 最終的にどのくらいのお金が手元に残るのか
また、「減価償却を上手に利用するスキル」も必要です。
不動産の種類や築年数により、1年に認められる減価償却費の金額が変わります。
減価償却費の金額を正確に把握して利用しなければ、節税はできません。
こうしたシミュレーションを、高い精度で行っていくためには、以下の本が役立ちます。
ぜひ、参考にしてみてください。
出典:amazon 「Excelでできる不動産投資「収益計算」のすべて」
(3)法人化することでさらに節税効果を期待できる
不動産投資をするとき、一定以上の収益が上がるようになったら、個人ではなく法人となる方が、節税効果が上がりやすくなります。
給与収入と不動産収入の合計額(年収)が1300万円を超えると、個人にかかる所得税率より法人税率の方が低くなるからです。
ケースにもよりますが、およそ7~17%程度、税率が下がります。
また、家族を役員にして所得を分散することも可能です。その方が、所得税率が下がります。
法人の株式評価額が低いうちに、相続予定者に生前贈与すれば、贈与税をほとんどかけずに財産を引き継げるため、相続税の節税にもなります。
法人設立での節税について、詳しくは「資産管理会社を活用した節税の仕組みと3大テクニック」こちらの記事で紹介しておりますので、あわせてご参照ください。
(4)「青色申告」でさらに節税対策できる
税務署に開業届を提出して、青色申告承認申請書を提出すれば、確定申告で「青色申告」をすることができます。
青色申告をすることで、65万または10万円の所得控除が受けられるので、さらに節税対策となると言えるでしょう。
具体的には、青色申告をすると、課税対象となる収入額から65万または10万円が引かれることになります。
課税対象となる金額が減るため、所得税自体が安くなるというメリットがあります。
青色で確定申告するには、下記のタイミングで、税務署へ「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
- 開業届を提出するタイミング
- 青色申告する予定の年の3月15日まで
一度申請しておけば、毎年申請する必要はありません。
しかし、青色申告は、複式簿記で帳簿をつけるなど手間がかかるため、事前に方法などをしっかり確認しましょう。
4、不動産投資でどのくらい節税ができるのか

それでは、不動産投資をすると、具体的にどこまで節税できるのでしょうか。
年収500万円のサラリーマンが、不動産投資をしていない場合とした場合の事例で考えてみましょう。
(1)不動産投資をしていない場合
| 給与所得 | 5,000,000 |
| 所得税 | 528,736 |
| 住民税 | 250,500 |
| ①+② | 779,236 |
(2)不動産投資をしてマイナス500,000円の不動産所得だった場合
| 給与所得 | 5,000,000 |
| 不動産所得 | −500,000 |
| 所得合計 | 4,500,000 |
| 所得税① | 333,500 |
| 住民税② | 235,000 |
| ①+② | 570,000 |
(1)で紹介した「不動産投資をしていない場合」の税額は、779,236円でした。
一方、不動産投資(不動産所得−500,000円)場合の税額は、570,000円となりました。
差額は実に210,736円と算出され、この事例だと、年間21万円あまりの節税が可能となりました。
5、不動産投資で節税する際の注意点5つ

ここまで、不動産投資による節税について解説してきましたが、不動産投資で節税をする際には注意点もあります。
具体的な注意点としては、以下の5点が挙げられます。
- キャッシュフローが悪くなる可能性
- 金融機関から融資を受けにくくなる
- 家賃引き下げや金利上昇などのリスク
- 耐用年数の経過
- 損益通算の注意点
(1)キャッシュフローが悪くなる可能性
節税を重視しすぎると、不動産投資のキャッシュフローが落ちる可能性があります。
個人で不動産投資で節税する場合、不動産投資における所得は、赤字になることが前提です。
いかに減価償却を上手に利用しても、大きく利益が出ている状態では、節税はできません。
節税するために収益を抑えてしまったら、「儲けを出したい」という不動産投資の目的から外れてしまい、本末転倒になってしまいます。
(2)金融機関から融資を受けにくくなる
不動産投資をするに際して、「融資」は必須です。融資を受けるためには、金融機関との関係が非常に重要となります。
赤字経営になると、金融機関の印象が悪化して、アパートローンを利用しにくくなります。
前述したように、不動産投資における節税は、赤字で計上することが前提です。
しかし、節税のために赤字を出し続けることは、投資資金を確保できなくなることに繋がるため、注意が必要です。
(3)家賃引き下げや金利上昇などのリスクに耐えられなくなる
不動産投資をするときには、物価の下落リスクや金利上昇リスクなど、さまざまなリスクがあります。
赤字経営で節税をする場合、ギリギリのところで経営しているケースが多いでしょう。
上記のようなリスク要因が現実化すると、一気に収益が悪化して、毎月の収支が著しく悪化する可能性があります。
収支が悪化すると、節税どころではなくなってしまい、不動産投資を続けることも難しくなるでしょう。
(4)耐用年数の経過
不動産投資による節税は、減価償却費の利用に頼るところが大きいですが、耐用年数が終わると、減価償却できなくなります。
減価償却できなくなると、不動産所得が黒字化して、一気に税金が増えてしまうリスクがあります。
節税のため、ギリギリの収益で運営していた場合は、税金が上がってローンや諸費用などの支払いが厳しくなるため、注意が必要です。
耐用年数が過ぎた古い物件の場合、売却しようとしても、簡単に買い手を見つけられない点にも注意しましょう。
(5)損益通算で注意したいこと
不動産物件を購入したばかりでは、多くの初期費用がかかるため、赤字になるケースが多くなります。
損益通算とは、別の黒字所得の課税対象金額から、不動産投資の赤字分を控除できる制度です。
具体的には、本業の会社員として働いた年収の課税対象金額から、不動産投資の赤字分が引かれます。
引かれた金額が、所得税の課税対象となるのです。不動産投資でいうと、例えば、「ローンの利息分」を経費として計上できます。
しかし、利息のうち土地分については、損益通算の対象にはならないので注意しましょう。
確定申告において、土地分の利息金額は、不動産所得用の青色申告や収支内訳書の「土地等を取得するために要した負債の利子の額」へ記載します。
その金額が、利息のうち「損益通算の対象にならない部分」となるのです。
6、不動産投資の魅力は節税だけではない

前章「5、不動産投資で節税する際の注意点」で解説した通り、不動産投資で節税するためには、大きなリスクが発生する可能性があることがわかりました。
不動産投資では節税対策ができますが、節税ばかりに目を向けてしまうと、本来の不動産投資の魅力を活かすことができません。
不動産投資で最も魅力的なのは、「レバレッジを効かせること」といえます。
金融機関から融資を受けることで、自己資金が少なくても、安定した収入を得ることができることが魅力です。
株式投資などでは、自己資金が必要となります。信用取引も可能ですが、保証金を納める必要もあります。
株式投資などでは、暴落などで一気に損失が出てしまうかもしれません。
一方で、不動産投資は、一気に不動産の価値が無くなったり、家賃が安くなったりすることはありません。
他の投資に比べて、ある程度安定した投資と言えるのです。
安定した収入が得られるようになると、不動産投資にはさらに以下のような魅力が考えられます。
- 老後も不労所得を得られる
- 老後の私的年金として活用でき安心できる
- 不動産として相続でき、結果として節税対策になる
7、不動産投資の節税に関する悩みは専門家に相談しよう

不動産投資で節税を狙うには、専門的な知識が不可欠です。
個人投資家が、法的な知識や不動産に関する情報全てを網羅することは、非常に難しいといえます。
そこで、専門家の手を上手く借りることが重要です。
本章では、不動産投資の節税について、誰にどのようなことを相談すればいいのか、説明します。
(1)節税対策で不動産投資をしている経験者に相談する
確定申告や節税対策の相談をしたい場合は、税理士に相談するのが基本です。
しかり、より具体的な不動産投資の節税対策について聞くなら、不動産投資の経験者に相談するのも有効な方法といえるでしょう。
成功体験や失敗体験も含めて、利害関係のない立ち位置での実践的なアドバイスを得ることができます。
大家さんや投資家の集まるセミナーなどに参加することで、相談の機会を得られるので、積極的に参加してみるといいでしょう。
(2)不動産投資会社に相談する
不動産投資を行うのであれば、パートナーとなる不動産投資会社に相談することは欠かせません。
良好な関係を築くことで、有益な情報を得られることが期待できます。
信頼できる会社を見つけることは、投資の成功に直結するでしょう。
ただ、不動産投資会社は、相談してきた相手との契約を狙っていることが基本です。
より客観的な情報やアドバイスを受けたい場合には、別の相談先を見つける必要があるでしょう。
(3)セカンド・オピニオンで客観的にアドバイスをもらう
不動産投資では、その物件が本当に買いなのかを判断するために、当事者に近い不動産投資会社以外のプロからセカンド・オピニオンを受けることが重要になります。
セカンド・オピニオンの候補は、以下のような相談先です。
- 不動産投資仲間や先輩
- 銀行員やFP
- 不動産投資に詳しい税理士や会計士 など
そして、意外にも有益なセカンド・オピニオンの相談先として、収益物件の近くにある不動産管理会社が挙げられます。
以下のような重要な情報を得られる可能性があるので、何社か訪問しておくといいでしょう。
- 賃貸需要
- 家賃相場の妥当性
- 地元でしか得られない重大な情報(もともと沼地で災害に弱いエリアであるなど)
まとめ
不動産投資の節税に関する悩みは解決できたでしょうか?
不動産投資によって、節税を期待できるということがわかりました。
ただし、節税効果が見込める場合は不動産所得が赤字の場合に限ります。
節税を追い求めすぎて、キャッシュフローが悪化することもあるので、不動産投資をする際には節税とキャッシュフローのバランスを取って、賢く進めていきましょう。