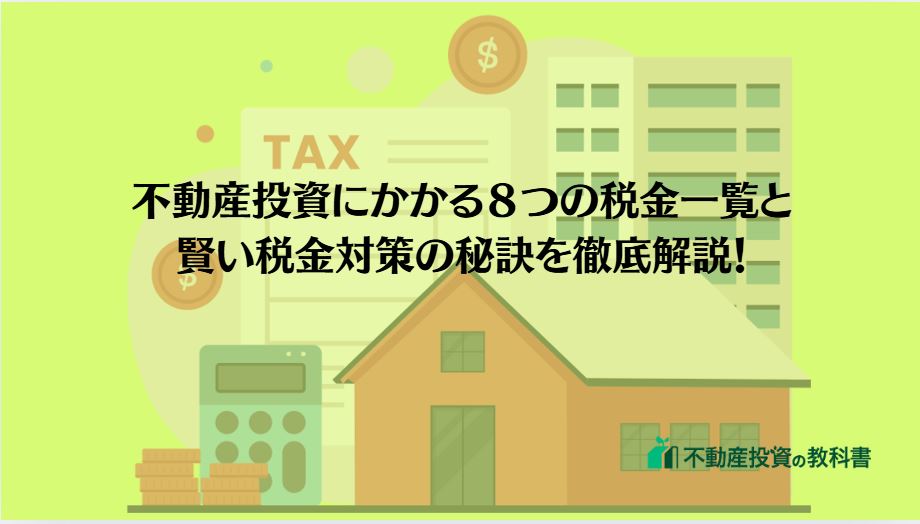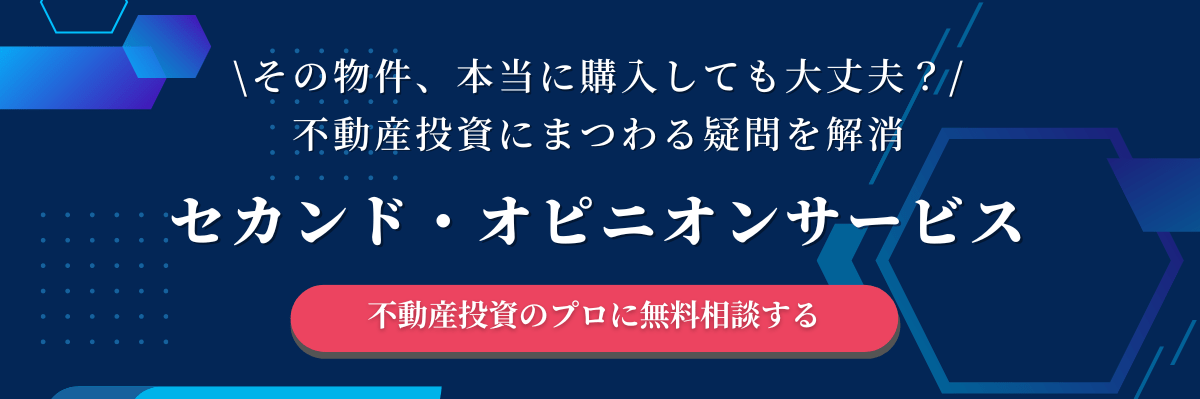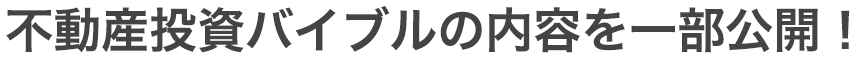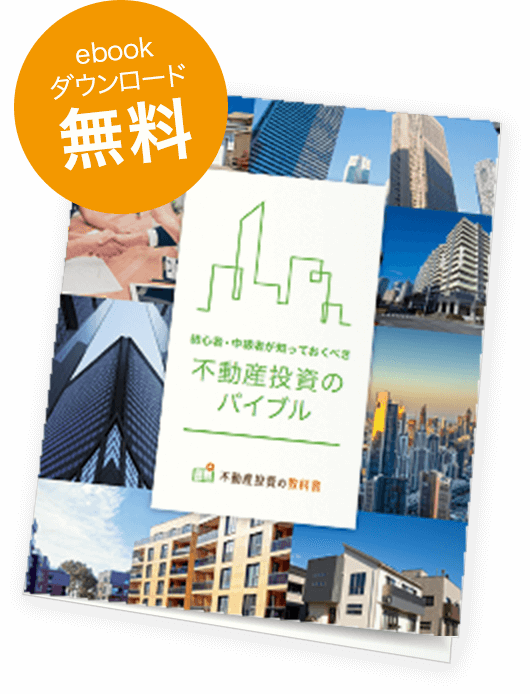不動産投資において、いつ、どのような税金がかかるかご存知でしょうか。
不動産投資をしたいと考えている方や不動産投資を始めたての方は、「不動産投資で節税したい!」とお考えの方も多いかと思います。
そこで今回は、以下の税金について解説していきます。
- 不動産投資でかかる8つの税金(取得時、所有時、売却時)
- 不動産投資における税金シミュレーション
不動産投資における税金に関する疑問や不安を解決するために、この記事をご参考いただければ幸いです。
以下の記事も参考にしてみてください。
不動産経営のメリットを解説|リスクを取る価値はあるのか【初心者向け】
目次
1、不動産投資で不動産取得時に課される3つの税金

不動産を取得する場合には、印紙税と登録免許税、不動産取得税が課されます。
それぞれの税金について、詳しくみてみましょう。
(1)印紙税
①税金の内容
印紙税とは、売買契約書や領収書などの書類に対して課される税金です。印紙税を添付することで、正式な書類としての効力を担保する意味合いがあります。
それぞれ書類の性質、記載金額によって納付する税額が異なるのが特徴です。書類1通につき定められた金額の収入印紙を貼付し、割り印などをして納付します。
不動産の購入において締結する売買契約書は、買主と売主双方1通ずつ所有しますが、その契約書それぞれに印紙税が課されます。
そのほかにも、新築時の「建築請負契約書」や住宅ローン時の「金銭消費貸借契約書」を作成する際にも、納付しなければいけません。契約書を作成するときは、基本的に必要になると考えておきましょう。
なお、令和6年3月31日までの間に作成した不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書については、軽減税率が適用されています。
印紙税の納付額は、以下のとおりです。
|
不動産売買契約書記載の金額 |
本則税率 |
軽減税率適用後 |
|
10万円以下 |
200円 |
200円 |
|
10万円超50万円以下 |
400円 |
200円 |
|
50万円超100万円以下 |
1,000円 |
500円 |
|
100万円超500万円以下 |
2,000円 |
1,000円 |
|
500万円超1000万円以下 |
10,000円 |
5,000円 |
|
1,000万円超5,000万円以下 |
20,000円 |
10,000円 |
|
5,000万円超1億円以下 |
60,000円 |
30,000円 |
|
1億円超5億円以下 |
100,000円 |
60,000円 |
|
5億円超10億円以下 |
200,000円 |
160,000円 |
|
10億円超50億円以下 |
400,000円 |
320,000円 |
|
50億円超 |
600,000円 |
480,000円 |
②節税できる税金か?
印紙税は納付が義務付けられているため、節税できません。
(2)登録免許税
①税金の内容
登録免許税は、会社や不動産などの登記をする場合に課される税金です。
登記とは、不動産の権利や物理的な概要を公示するために登記簿に記載することで、不動産を管轄する法務局または出張所に備え付けられています。購入した不動産が自分のものであることを公に証明するための記録であり、通常は不動産購入後すぐに所有権の登記が行われます。登記にはさまざまな種類があり、不動産の取得の仕方によっても分類されている点には注意しましょう。
マイホームを新築で建てた場合は「所有権保存登記」、中古で購入した場合はすでに前の所有者が所有権保存登記を行っているので、「所有権移転登記」になります。
また、住宅ローンなどを組む際に不動産を担保にするときは抵当権の設定が必要な場合があります。抵当権の設定も登記のひとつです。
登録免許税の計算は、固定資産税評価額や債権額に一定の割合をかける仕組みです。
固定資産税評価額とは、不動産を所有していると毎年かかる固定資産税の算出基礎となっている価格のことで、3年に一度評価替えが行われ市町村長が価格を決定しています。なお、登録免許税も印紙税と同じように軽減措置(令和6年3月31日まで)がありますが、あくまでも自己居住用のみが対象です。
投資用不動産の場合、登録免許税は軽減措置の対象にならないので注意しましょう。
登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
|
登記の内容 |
登録免許税の計算 |
軽減税率適用後 |
|
所有権の保存登記 |
固定資産税評価額×0.4% |
固定資産税評価額×0.15% |
|
所有権の移転登記(土地) |
固定資産税評価額×2% |
固定資産税評価額×1.5% |
|
所有権の移転登記(建物) |
固定資産税評価額×2% |
固定資産税評価額×0.3% |
|
抵当権の設定 |
債権額×0.4% |
債権額×0.1% |
②節税できる税金か?
登録免許税は節税できません。
(3)不動産取得税
①税金の内容
不動産取得税とは、家屋や土地を購入したり、家屋を建築したりなどで不動産を取得したときにかかる税金です。
不動産を取得してから大体6ヶ月後くらいに、不動産の所在地を管轄する県税事務所から納税書が郵送で送られます。
不動産取得税は、不動産取得時に1回だけ納める税金です。
不動産取得税にも軽減措置はありますが、税率が低くなるだけでなく不動産の種類によっては算出の基礎となる評価額を控除する場合もあります。
建物の場合、新築であれば1,200万円の控除となりますが、長期優良住宅は1,300万円です。中古住宅は、新築年月日によって控除額は変動するので注意しましょう。
税額の計算方法については、下記表をご参照ください。
|
取得対象 |
本則税率 |
軽減税率 |
|
土地(住宅用) |
固定資産税評価額 × 4% |
固定資産税評価額 × 1/2 × 3% |
|
建物(新築) |
固定資産税評価額 × 4% |
(固定資産税評価額-1,200万円)× 3% |
②節税できる税金か?
不動産取得税は、節税できません。
2、不動産投資で不動産所有時に課される2つの税金

不動産を所有していると、税金がかかります。
具体的な税金は、固定資産税・都市計画税です。
不動産投資による家賃収入がある場合には、所得税も課されます。
それぞれの税金についてみてみましょう。
(1)固定資産税・都市計画税
①税金の内容
固定資産税・都市計画税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金です。固定資産の価格をもとに算定された税額を、所有不動産の所在する市町村に納めます。
毎年4~6月ぐらいにかけて納税通知書が届き、一括または年4回納税します。年4回に分納する場合の支払い月は、東京23区の場合6月、9月、12月、翌年2月です。
固定資産税と都市計画税には、課税標準額に一定の割合を掛けて算出する軽減措置があります。軽減措置による減額幅は比較的大きく、対象になれば大幅な節税に貢献するでしょう。ただし、軽減措置が適用されるためには要件があるため注意しましょう。面積が50平米以上なくてはならなかったり、3年や5年などの年数制限があったりします。
特に面積要件については、ワンルームマンションでは満たしていない恐れがあるので事前にしっかり確認しましょう。
固定資産税、都市計画税の標準的な税額
| 税金 | 計算方法 |
| 固定資産税 | 固定資産税評価額 × 1.4% |
| 都市計画税 | 固定資産税評価額 × 0.3% |
軽減措置が適用された場合の固定資産税の計算方法
|
建物や土地の種類 |
計算方法 |
|
新築建物 |
固定資産税評価額 × 1.4% × 1/2 |
|
小規模住宅用地(200平米以下の部分) |
固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4% |
|
一般住宅用地(200平米を超える部分) |
固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4% |
軽減措置が適用された場合の都市計画税の計算方法
|
建物や土地の種類 |
計算方法 |
|
新築建物 |
軽減措置なし |
|
小規模住宅用地(200平米以下の部分) |
固定資産税評価額 × 1/3 × 0.3% |
|
一般住宅用地(200平米を超える部分) |
固定資産税評価額 × 2/3 × 0.3% |
②節税できる税金か?
固定資産税と都市計画税は節税できません。
(2)不動産所得税
①税金の内容
所得税は、土地や建物などの不動産の貸付けることによって生じる所得(家賃・地代・権利金)に対して課される税金です。
不動産所得は総合課税として計算しますので、「所得税の税率」に従って、5%から45%の7段階に区分されています。
|
所得税の速算表 |
||
|
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
|
195万円以下 |
5% |
0円 |
|
195万円を超え330万円以下 |
10% |
97,500円 |
|
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427,500円 |
|
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636,000円 |
|
900万円を超え1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
|
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
|
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
所得税額は、下記の計算式によって計算されます。
「所得税額=(総収入金額-必要経費-所得控除) × 税率-税額控除」
総収入金額には、月々の家賃以外にも礼金や更新料なども含まれます。
必要経費は、事業用不動産に課されている固定資産税などの税金や不動産会社に支払う管理費、借入金の利息(ただし、不動産所得が赤字の場合は土地の支払い利息分は対象外)などです。
不動産所得の所得税は、他の所得と合計する総合課税として計算し、確定申告によって税額を確定され納付します。サラリーマンの所得税は、基本的に年末調整によって所得税額が確定します。サラリーマンの方で、不動産投資など本業以外の事業によって年間20万円を超える所得があるという方もいらっしゃいます。
そのような場合には、本業以外の所得についてご自身もしくは税理士に代行してもらって確定申告をする必要があるため、注意しましょう。
②節税できる税金か?
所得税は節税できます。
③節税方法
所得税を節税するためには、必要経費をきちんと計上して所得額を低く抑えることがポイントです。
総収入には、次の費用が含まれています。
- 給与所得
- 家賃収入
- 礼金・保証金など
- その他収入(株、FXなど)
不動産投資において、認められている経費を確認しましょう。
- 税金(固定資産税、都市計画税など)
- 損害保険料(火災保険、地震保険など)
- 修繕費(入居者が退去時のクリーニング費用など)
- 賃貸管理会社管理費
- 建物の減価償却
- マンション管理会社管理費(管理費、修繕積立金など)
- 税理士・弁護士などへの報酬
- その他経費(交通費、ガソリン費用、交際費など)
- 賃貸開始後に支払った借入金の利息(融資を受けた場合)
3、不動産投資にて不動産売却時に課される3つの税金

不動産売却時に課される税金には、印紙税と登録免許税、譲渡所得税があります。
必ず課される税金は、印紙税のみです。
登録免許税は不動産購入時に融資を受けた場合、譲渡所得税は売却益が出た場合のみに課されます。
それぞれの税金についてみてみましょう。
(1)印紙税
①税金の内容
不動産購入時の場合と同様に、売買契約書に貼付される印紙のことです。
税率なども購入時と同じなので、「1、不動産取得時に課される税金(1)印紙税」の項目をご参考ください。
②節税できる税金か?
印紙税は納付が義務付けられているため、節税できません。
③節税方法
印紙税は、不動産売買契約書に課される税金です。一般的には、不動産売買契約書を2通作成し、買主と売主が1通ずつ所有します。買主と売主はそれぞれ1通の印紙税を負担します。
不動産売買契約書において印紙税を節税するには、不動産売買契約書をコピーで持ちましょう。買主は必ず不動産売買契約書の原本を持つ必要があるため、購入時の売買契約書に貼付する印紙代は負担せざるを得ません。
しかし、売主は必ずしも原本で所持する必要がないので、原本をコピーすることで、本来売主が負担する印紙代を節約できます。
(2)登録免許税(抵当権抹消が必要な場合)
①税金の内容
「1、不動産取得時に課される税金(2)登録免許税」で説明したように、登録免許税が課されますが、売却時にも登録免許税がかかります。
購入時の登録免許税は、不動産の「登記」に対して課される税金です。
一方、売却時の登録免許税は、不動産の抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)に対してかかる税金です。
不動産売却時の登録免許税の仕組みについて、もう少し詳しく説明します。
不動産を購入する際、金融機関から融資を受けて購入するというケースがほとんどです。
金融機関から融資を受けた場合には、不動産に「抵当権」が設置されます。
融資を受けて購入した不動産を売却する際には、この抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権抹消のためには、不動産購入時に金融機関から受けた残りの融資を売却費を利用して一括返済する必要があります。
つまり、不動産売却時の登録免許税は、金融機関から融資を受けた場合のみ課される税金です。
②節税できる税金か?
不動産売却時の登録免許税についても、不動産購入時と同様に節税できません。
(3)譲渡所得税(売却益が出た場合)
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得税とは、譲渡所得に売却益が出た場合にのみかかる税金です。
①譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、下記の計算式にて簡単に計算できます。
「譲渡所得=売却金額―取得費―譲渡費用(仲介手数料など)」
②譲渡取得税の税率
譲渡所得税の税率は、「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」によって異なります。
不動産を売った年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が「5年」を超えているかどうかが判断基準です。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
③譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得税=譲渡所得 × 税率
④節税できる税金か?
譲渡所得税は節税できます。
⑤節税方法
諸経費を高く計上して利益額を低くすることによって、譲渡所得税の節税が可能です。
諸経費として認められる費用について確認してみましょう。
- 購入時の諸経費(仲介手数料、登記費用、不動産取得税など)
- 売却時の諸経費(仲介手数料、印紙税など)
購入時の諸経費が分からないという場合には、売却価格の「5%」として計算することもできます。
売却価格が高い場合は、売却価格の「5%」で計算することで節税となる場合もありますので、ご参考にしてください。
以上のように、不動産投資をしていくなかで、いつどのような税金が課されるかについてご理解いただけましたでしょうか。
続きまして、サラリーマンの方が不動産投資をした場合の、所得税のシュミレーションを紹介します。
4、不動産投資における税金のシミュレーション

不動産所得は、総合課税として計算します。
サラリーマンの方の不動産所得は、給与所得に加算して課税されます。
(1)所得税額の計算方法
所得税額は、下記の式で計算します。
所得税額=(総収入金額-必要経費-所得控除)× 税率-税額控除
(2)税金のシミュレーション
では、実際にサラリーマンの方が不動産投資をした場合の所得税についてシミュレーションしてみましょう。
下記の不動産情報や借入条件を前提にして、算出しました。
①年間収支
| 年間収入額 | ||
| 家賃収入額 | ① | 960,000 |
| 給与所得
※給与所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額 |
② | 5,000,000 |
| 収入合計額(①+②) | ③ | 5,960,000 |
| 不動産諸経費 | ||
| 固定資産税 | ④ | 60,000 |
| 管理・修繕費 | ⑤ | 193,320 |
| PM会社費用 | ⑥ | 51,840 |
| 損害保険料 (火災・地震保険など) |
⑦ | 20,000 |
| 減価償却費 ※1,500万(物件取得費用) × 0.028減価償却率) |
⑧ | 420,000 |
| 借入金利子 | ⑨ | 283,660 |
| 税理士報酬 | ⑩ | 50,000 |
| 合計(④~⑩合計) | ⑪ | 1,078,820 |
③所得税計算
| 所得税計算 | ||
| 所得金額(③-⑪) | ⑫ | 4,881,180 |
| 青色申告控除 | ⑬ | 100,000 |
| 課税対象額(⑫-⑬) | ⑭ | 4,781,180 |
| 給与所得と不動産所得を合算した場合の所得税額 ※⑭ × 20%-427,500円 |
⑮ | 528,736 |
|
給与所得のみの所得税額 ※② × 20%-427,500円 |
⑯ | 572,500 |
| 所得税の差額(⑯-⑮) | ⑰ | -43,764 |
※所得税の計算にあたって復興特別所得税や所得控除等は加味していません。
(3)確定申告は会計ソフトで簡単にできる
上記のシュミレーションは、青色申告という種類の確定申告をしている前提となっている点に注目してください。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告の方が控除額が大きい代わりに複雑な帳簿付けが必要になるため、初心者にはハードルが高いと感じるかもしれません。
しかし、クラウド型の会計ソフトを使うことで、銀行口座やクレジットカードの取引データの入力を自動化でき、手間や時間をかけずに帳簿付けができます。
また、確定申告に必要な書類を、質問に答えていくだけで作成してくれるので、初心者でもオンライン上で提出まですることができるのです。
よく使われている、代表的な会計ソフトを3つ紹介します。
freee
 出典:freee
出典:freee
日常の取引入力から確定申告まで完結する、クラウド会計ソフトです。
専用アプリが非常に使いやすく、会計業務のほとんどがスマホで作業できるため、出先での空いた時間にも取引入力ができます。
確定申告書類も、基本的には質問に答えていくだけで自動的に作成してくれたりとシンプルで使いやすいため、「不動産投資の教科書」が一番おすすめするソフトです。
マネーフォワード
 出典:マネーフォワード
出典:マネーフォワード
マネーフォワードは、小規模法人から上場企業まで、さまざまな規模の会計業務をサポートするクラウド会計ソフトです。
そのため、将来的に事業拡大を計画しているケースで、有効活用できるでしょう。
個人事業主向けのプランもあるため、事業の規模や月々の料金、サポート内容などから最適のプランを選べます。
弥生会計オンライン
 出典:弥生会計オンライン
出典:弥生会計オンライン
1987年に販売開始の会計ソフト「弥生」シリーズのクラウド版です。古くからの実績があり、22年連続売上1位を誇ります。
簿記の知識がほとんどない人にも使いやすい設計で、サポート体制も充実しています。
(4)不動産投資が節税となることがある?
①節税となるケースとは?
サラリーマンの方による不動産投資において、家賃収入より経費が上回っている場合、 源泉徴収された給与所得の所得税が還付されます。
仮に不動産所得が黒字になっても、費用計上をしっかりしていれば、給与所得と不動産所得のそのままの合計より節税されるはずです。
節税になるからといって帳簿上の赤字を狙いすぎると、経営が悪くなる恐れもあります。
忘れずに費用計上を行い、基本的には黒字を目指すとよいでしょう。
②上記シミュレーションの場合は節税できる?
(2)のシミュレーションも節税となるケースです。
給与だけの収入では、572,500円の所得税でした。
しかし、不動産収入と合算すると最終的に「528,736円」になり、約4万円の節税ができています。
所得税と同じように、所得額をもとに算出する住民税の節税も期待できるでしょう。
このように、サラリーマンの場合、不動産投資をすれば所得税を節税できるケースがあります。
詳細は、「不動産投資の節税について解説|節税対象になるのはどんな人?」にて紹介しておりますので、ご参照ください。
まとめ
今回は、不動産投資においてかかる税金について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
不動産投資の状況によってさまざまな税金がかかることがわかりましたね。
また、サラリーマンが本業の傍ら不動産投資を行うと、所得税や住民税を節税できるというメリットがあります。
これから不動産投資を始めたいと考えている方は、この記事をご参考にしていただき、節税をうまく取り入れた不動産投資を目指してください。