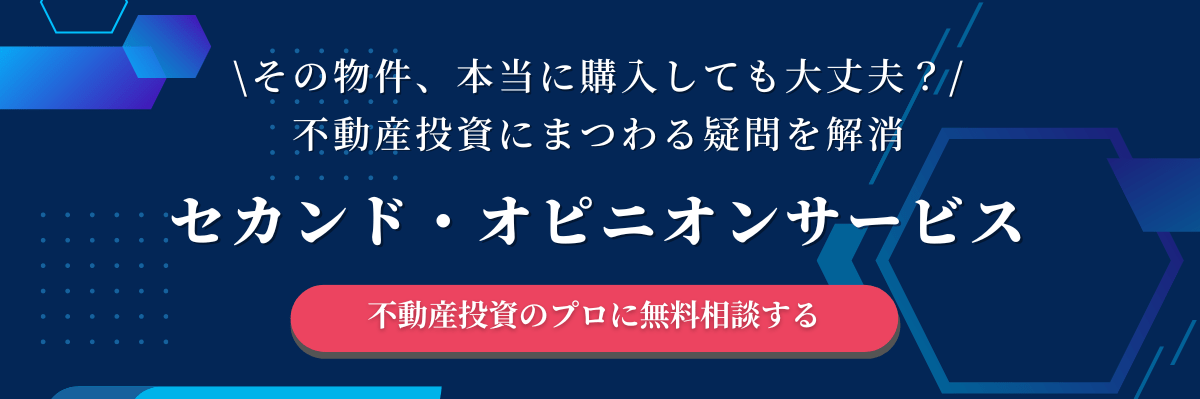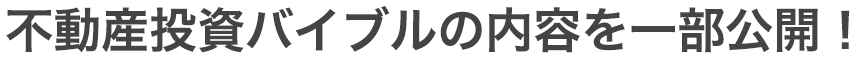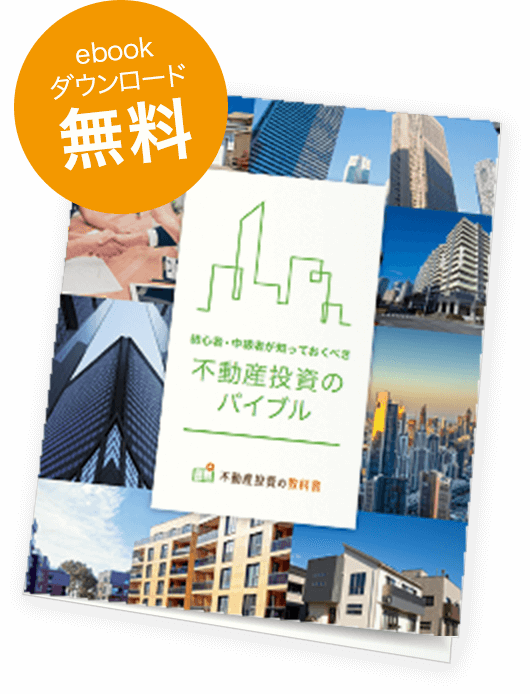アパート経営を考えているけれど、税金はどのくらいかかるのか?という疑問に答えます。
節税ができるのに対策しないのは、とてももったいないことです。節税対策や税金の種類について理解し、収益を最大化しましょう。
アパート経営をするときには、主に7種類の税金がかかってきます。
そこで今回は、
- アパート経営をする際にかかる7種類の税金とは?
- アパート経営をする際の節税方法とは?
- それぞれの税金の支払い方
を解説していきます。
今回の記事をご覧の方は、ぜひ以下の記事も併せてご覧ください。
アパート経営における経費の節税で得するための6つのこと

フドウくん
目次
1、アパート経営にかかる税金の種類
 アパート経営をするとき、かかる可能性のある税金の種類は以下の7種類です。
アパート経営をするとき、かかる可能性のある税金の種類は以下の7種類です。
税金をパターンごとに分類し、相対的に重要なものから順に並べていきます。
(1) 不動産保有中にかかる税金
まずは、不動産保有中にかかる税金です。
- 所得税 →詳しくは「2、所得税の計算方法と節税方法と具体的な支払い方」をご参照ください
- 住民税 →詳しくは「3、住民税の計算方法と節税方法と具体的な支払い方」をご参照ください
- 固定資産税 →詳しくは「4、固定資産税の計算方法と節税方法と具体的な支払い方」をご参照ください
- 消費税(場合によっては) →詳しくは「5、消費税を支払う必要があるケースとは?」をご参照ください
(2) 不動産売却時にかかる税金
次は、不動産売却時にかかる税金です
- 譲渡所得税 →詳しくは「6、不動産譲渡所得税の計算方法と節税方法と具体的な支払い方」をご参照ください
(3) 不動産購入時にかかる税金
最後に、不動産購入時にかかる税金です。
- 不動産取得税 →詳しくは「7、不動産取得税の計算方法と具体的な支払い方」をご参照ください
- 登録免許税 →詳しくは「8、不動産登録免許税の計算方法と具体的な支払い方法」をご参照ください
時系列では、購入時→保有中→売却時という順番ですが、相対的に重要な順番ということで、保有中→売却時→購入時という順番となっています。
次章では、それぞれがどのような税金で、どのようにして計算するのかを説明します。
2、アパート経営の税金|①所得税
 まずは、所得税の計算方法と節税方法です。
まずは、所得税の計算方法と節税方法です。
(1)税金の計算方法
所得税とは、不動産収入によって所得が発生したときにかかる税金です。つまり、アパート経営で賃料収入を得て利益が発生すると、所得税がかかります。
なお、所得 = 利益です。
所得税を計算するときには、まずは家賃収入から必要経費を引きます。
不動産収入 – 経費 = 不動産所得です。
また、所得税率は所得の総額によって異なるので、給与所得などの別の所得がある場合には、その所得も合算して全体としての所得を算出する必要があります。
そうして得られた合計所得に対応する所得税率を、不動産所得に対してかけ算すれば、不動産収入に対する所得税を算出できます。
(2)具体的計算事例
給与所得 500万円、不動産所得 120万円のケース
この例では、給与所得の控除額は100万円とします。
まず、所得 = 給与所得500万円 – 所得控除100万円 + 不動産所得120万円 = 520万円です。
520万円に対する所得税率は、20%です。
そこで、不動産所得に対する所得税の金額は、120万円 × 20% = 24万円となります。
(3)節税方法
所得税を節税するためには、経費を確実に算入することが重要です。経費として認められるものは、以下のような費目です。
- 借入金の利子
- 減価償却費
- 租税公課(登録免許税や不動産取得税、印紙税や固定資産税など)
- 修繕費用
- 損害保険料
- 管理会社の費用
- 水道光熱費
- 取り壊し費用
- 立ち退き費用
経費の支払いをしたら、必ず領収証を保管して、確実に所得を減らしましょう。
(4)確定申告について
アパート経営によって収益を得たら、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、税金を納めるための手続きです。
事業所得や不動産所得がある場合には、翌年の2月16日から3月15日までの間に、自ら税務署で確定申告をして、所得税の納税をしなければなりません。
源泉徴収などで税金が過払いになっている場合には、確定申告によって税金の還付を受けられ、メリットとなるケースもあります。
不動産収入の確定申告をするとき、まずは源泉徴収票や家賃管理明細書、経費の支払いに関する帳簿などを手元に用意します。
そして、収支内訳書と確定申告書Bという書類を作成して、税務署に提出します。
納税が必要であれば計算された税金を支払いますし、過払いがあれば口座を指定して還付してもらうことができます。
詳しい申告方法については、「【税理士が教える】サラリーマンが確定申告で還付が受けられる6つのケース」のページをご参照下さい。
(5)青色申告にするか、白色申告にするか
所得税の申告方法としては、青色申告と白色申告があります。
青色申告にすると多少手間はかかりますが、最大65万円分の特別控除を受けられるメリットがあります。
そこで、アパート経営が小規模であれば白色申告でもかまいませんが、それなりに規模が大きくなってきたら青色申告を適用した方が良いでしょう。青色申告を適用するには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署宛に提出する必要があります。
青色申告は、白色申告に比べて複雑な帳簿付けが必要になりますが、会計ソフトを利用することで、初心者でも帳簿付けや確定申告がかんたんにできます。
freeeを使うと、銀行口座やクレジットカードの取引データの入力を自動化できたり、指示通りに入力していくだけで確定申告に必要な書類を作成、提出まですることができます。
本業があり、時間や手間をあまりかけられない、という方に「不動産投資の教科書」が一番おすすめする会計ソフトです。
3、アパート経営の税金|②住民税
 次は住民税です。
次は住民税です。
(1)税金の計算方法
アパート経営にかかる税金の2つ目は、住民税です。住民税も、所得税と同様、所得(利益)に応じてかかるものです。
そこで、同じように不動産収入から経費を引いた所得に対する住民税の税率をかけ算して、住民税を計算します。
住民税は、都道府県税と市町村税があるので、両方を計算する必要があります。
また、住民税には所得割と均等割という部分があります。所得割は都道府県税の部分が6%、市町村税が4%となりますが、均等割は地域によって異なります。
(2)具体的計算事例
たとえば、給与が500万円、給与所得者控除が100万円、不動産所得が120万円の場合、所得合計は520万円です。
都道府県税の税率が6%、市町村税の税率が4%とすると、両方で52万円の住民税が課税されます(不動産所得にかかる分は12万円)。
これに、地域に応じた「均等割」という税金が加算されます。
(3)節税方法
住民税は、所得に応じて加算されるので、基本的な節税方法は所得税の節税方法と同じです。
なるべく多くの必要経費を算入して、所得を減らしたら、その分住民税が減額されます。
4、アパート経営の税金|③固定資産税
 アパートなどの不動産は、所有しているだけで税金がかかります。その税金が固定資産税です。
アパートなどの不動産は、所有しているだけで税金がかかります。その税金が固定資産税です。
(1)固定資産税とは?
不動産を所有していることに対する税金を「固定資産税」と言います。
固定資産税は、所有している不動産の評価額に応じて計算されます。
(2)固定資産税の計算方法は?
税率は、固定資産税評価額の1.4%です。固定資産税評価額は、不動産の時価とは異なり、通常は時価の7割程度となっています。
また、固定資産税評価額は3年に1回改定されます。不動産の所有者であれば、市町村役場で固定資産税評価証明書を取得することができるので、関心があったら1枚申請してみると良いでしょう。
たとえば、土地の固定資産税評価額が1,000万円、建物の評価額が1,200万円のアパートを経営する場合、年間にかかる固定資産税の金額は、以下の通りです。
2,200万円 × 1.4% = 308,000円
他に、アパートが市街化区域にある場合には、都市計画税という税金もかかります。
5、アパート経営の税金|④消費税
 不動産賃貸業において、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
不動産賃貸業において、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
一般居住用の賃貸の場合、消費税は不要です。これに対し、店舗や事業用物件としての貸し出しの場合、消費税を徴収することとなりますので、消費税の申告と納税が必要です。
前年度と前々年度の収入が1,000万円以下のケースでは、免税事業者となり消費税は課税されません。
2023年10月から、「インボイス制度」(正式名称は「適格請求書等保存方式」)が開始されます。インボイス制度とは、「適格請求書( = インボイス)」を発行・保存することで、正しく消費税額を計算し、適正な控除を受けるための仕組みのことです。
アパートやマンションなど住宅の家賃には基本的に消費税がかからないので、住宅賃貸を経営している場合は、ほとんどのケースでインボイス制度の影響はありません。
ただし、消費税が非課税になるのは、契約書に「住宅用であること」が明示されており、賃貸期間が1ヶ月以上である必要がありますので注意しましょう。
また、店舗や事業用物件の賃貸は消費税が課税されるため、インボイス制度の影響をうけることになります。インボイス制度への対策をする場合、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を完了させる必要があります。
2023年10月に始まるインボイス制度に自身が対応する必要があるかどうか、チェックしておきましょう。
6、アパート経営の税金|⑤不動産譲渡所得税
 次は、売却時にかかる譲渡所得税について説明していきます。
次は、売却時にかかる譲渡所得税について説明していきます。
(1)不動産譲渡所得税が発生する場合とは?
マンション経営に際して、不動産譲渡所得税という税金が発生するケースがあります。
これは、不動産を譲渡(売却)したことによって利益が出た場合、その利益( = 所得)に課税されるものです。
売却しても損失が出た場合には、譲渡所得税は発生しません。
(2)計算方法
譲渡所得税の計算方法は、以下のとおりです。
譲渡所得 = 不動産を売ったことによる収入 – 売却にかかった経費 – 不動産の取得費用 – 取得の際にかかった経費
これに、譲渡所得税の税率をかけ算します。5年を超えて不動産を所有していた場合には、長期譲渡所得として、税率が低くなります。
(3)節税方法
譲渡所得税を節税するためには、確実に経費(売却費用)や不動産取得費用を算入して、譲渡所得を減らすことが重要です。
たとえば、経費としては、以下のようなものがあげられます。
- 経費(売却費用)
- 測量費
- 建物の取り壊し費用
- 仲介手数料
- 所有権移転登記費用
- 印紙代
- 立退き料
- 広告料
- 不動産取得費用
不動産取得費用は、以下のようなものです。
- 購入代金
- 建築費用
- 測量費
- 整地費用
- 登記費用
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙代
- 不動産業者の仲介手数料
- 公正証書作成費用
また、5年を超えて不動産を所有していると、税率が低くなるので、売却するなら5年が経過するまで待つ方が節税になります。
(4)税金の支払い方
譲渡所得税についても、所得税と同様、翌年の確定申告によって納税します。
譲渡をした翌年の2月16日~3月15日までの間に管轄の税務署で確定申告を行い、計算された譲渡所得税を支払いましょう。
所得税と一緒に申告して納税すると良いでしょう。
7、アパート経営の税金|⑥不動産取得税
 次は、購入時に支払う必要がある不動産取得税の計算方法と、具体的な支払い方です。
次は、購入時に支払う必要がある不動産取得税の計算方法と、具体的な支払い方です。
(1)計算方法
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときにかかる税金です。
アパートの場合には、土地を取得したり建物を建てたりしたとき、都道府県から課税されます。
税率は、固定資産税評価額の4%ですが、居住用の資産である場合、3%に軽減されます。
さらに、床面積が50㎡~240㎡の場合、1室について建物評価額から1,200万円が控除されます。
(2)税金の支払い方法
不動産を取得すると、取得後60日以内に都道府県税事務所に申告する必要があります。
都道府県によっては30日以内や20日以内となっていることもあるので、注意が必要です。
申告をすると、都道府県税事務所から納付書が送られてくるので、それを使って金融機関などで納税します。
また、申告をしなくても、自動的に納付書が送られてくるケースもあります。そのような場合には、きちんと軽減措置が適用されているかどうか、チェックしておきましょう。
8、アパート経営の税金|⑦不動産登録免許税
 最後に、購入時にかかる不動産登録免許税です。
最後に、購入時にかかる不動産登録免許税です。
(1)計算方法
不動産登録免許税について、ご説明します。
不動産登録免許税は、不動産の各種の登記をするときに発生する税金です。
アパート経営では、新築時や所有権移転登記、抵当権設定登記をするときに必要となります。不動産の固定資産税評価額が基準となります。
新規にアパートを建てたときには「所有権保存登記」が必要です。その際の税率は0.4%です。
中古アパートを購入した場合には、「所有権移転登記」が必要です。その際建物取得にかかる登録免許税の税率は2%です。
土地についての所有権移転登記の登録免許税率は、1%となります。
アパートローンを設定するときには、「抵当権設定登記」が必要です。その際の税率は0.4%となります。
(2)税金の支払い方法
登録免許税については、基本的に現金によって支払うのが原則です。まずは金融機関で納税をして支払い調書を発行してもらい、それを登記申請書に貼り付けて納税します。オンラインによる納付も可能です。
ただ、実務的には印紙を使って納税することが多いです。
その場合、必要な金額の印紙を登記申請書に貼り付けて納税します。
アパート経営の税金に関するよくある質問
(1)「個人事業税」について教えてください。
個人事業税は、「事業的規模である」と認定された場合に課せられる税金です。基準は都道府県により多少ちがいますが、アパート経営では、おおむね10室以上の経営が該当します。
かつ、前年度の事業所得が290万円を超える事業者が、個人事業税を支払う対象となります。
(2)交通費や接待交際費などはアパート経営の経費になる?
交通費や接待交際費、消耗品費なども、アパート経営のために使用した場合は経費として計上できます。
例えば、経営するアパートや不動産会社に赴いた際の交通費や、経営に必要な事務作業に使用する文房具などが経費になります。
(3)アパート経営にかかる税金を含めた収支シミュレーションを見たいのですが……
複数の企業にまとめてプラン提案を依頼できる「HOME4U土地活用」を利用する方法があります。
最大10社まで無料でプランを出してもらえ、建築費だけでなく収支シミュレーションや将来的にかかってくるメンテナンス費用まで相談することができます。
まとめ
今回は、アパート経営に必要な税金について、1つずつ解説しました。
アパート経営を成功させるには、節税対策が重要なポイントになってきます。
アパート投資の際には、ぜひ参考になさってください。この記事が、アパート経営を成功に導く一助となれば幸いです。
武蔵コーポレーションの一棟管理
武蔵コーポレーションの「受託サブリース」をご存じでしょうか?
創業以来、一棟アパートの管理を手がけてきた武蔵コーポレーションは、中古アパートでも平均入居率97%を誇ります。
対応エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木ですが、22,000戸以上の管理実績を持っています。対象エリアのアパートのサブリースを検討している方は、ぜひ相談してみてください。